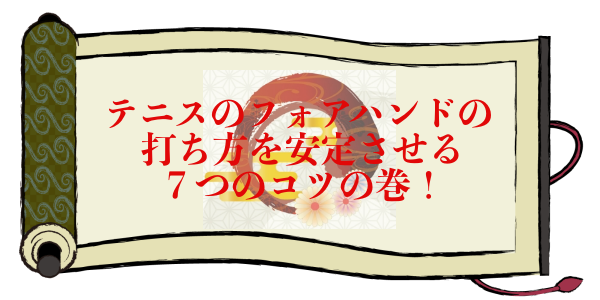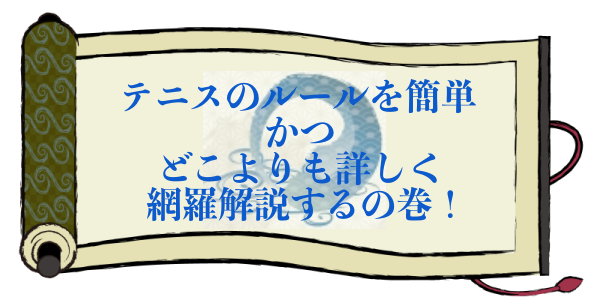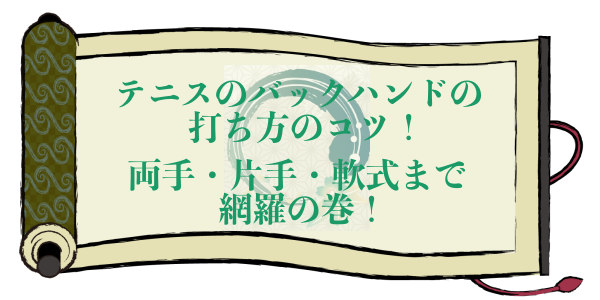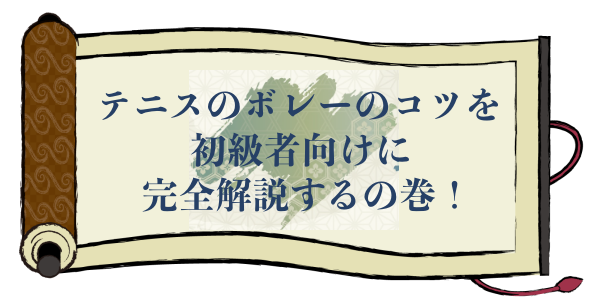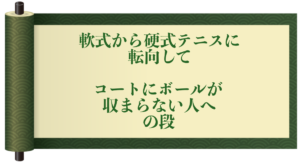テニスはある種期待値ゲームなので、安定してボールをコートに収めることは最もといっていいほど重要なことです。
ボールがネットにかかったり、飛んでいってしまったりしてばかりでは勝てるものも勝てません。
特に初中級ではほぼ相手のミスによる得点なので、如何に安定して淡々と返球し続けるかが重要になってきます。
ボールを安定させる上で、ひとつ、考え方のギャップになる部分だなと感じることがあったので少し書いてみたいと思います。
ボールを安定させるには小さく動かなければならない・・?
テニス始めたての頃は、とにかくボールを返そうとして当て返しというか、当てて返すだけになったりしますよね。
それが上達してきて少しずつラケットを振れるようになると、ミスしたときに周りからこう言われることがあります。
「まずは返そう。そんなに振らなくていいからコンパクトに。」
で、返そう返そうとして身体が萎縮して、ネット連発みたいな。
でも上手い人を見てると、みんな大きく伸び伸びと振っている。
自分も上手くなったらああいう風に振れるようになるはず、だから今はとにかく返すことに集中しよう。
ミスしたら周りからうるさく言われるし・・・。
そんなこんなであらゆる動きをコンパクトにしようと意識しているのに、いつまで経っても安定しない。
ああ自分には無理なのか。。。
上手いやつはあんなに振り回してミスしても笑ってるのに、なんで自分はこんなセコセコやらないといけないのか。
部活とかだとよくある光景じゃないでしょうか。
しっかりとした指導者がいるとこだとそんなことはないんでしょうけど。
で、↑のなにが良くないかって話なんですが、
動きを小さくコンパクトにすると、打点が近くなったり、手首をこね回すようになります。
テニスボールは物理法則に従って飛んでいきますので、ラケットとボールが接触する瞬間に全てが決まります(F=ma)。
なのに、打点が近い→飛ばない→手首で無理やり飛ばそうとする→ラケット面があらぬ方向を向く→ボールがあっちこっちへ飛び回る、となります。
違いますよね。
正解は
打点を遠くにとる→身体全体でスイングしなければ届かない→腕を伸ばさないと届かない→手首を使う必要がない→ラケット面が安定する→ボールが安定する
です。
コンパクトに、というのはスイングが安定して、体幹も安定して、面も安定している人が、最後にさらに安定性を高めるためにやることで、初心者がやることではありません(歳を取ったり、身体が満足に動かない場合はその限りではありませんが)。
そして初めにフォームを固めることの重要性は、ラケットとボールのインパクトの瞬間の面の向きや力の方向の再現性を高めるためだと言っても過言ではありません。
上手い人が大きく伸び伸びとスイングしているのは、それが一番安定すると知っているからで、決してパワープレーをしたいわけではないのです。
面の安定性が失われる、つまり面の向きが安定しないのは、多くの場合、手首を使ってしまっていることに起因します。
身体全体、腕全体でラケットを振ることによって、極力手首が動かないようにし、面がブレないように安定を図っているのです。
手打ちがいけない理由は、パワーが出ないことよりも、手首が動いて面とボールが安定しないことにあります。
打点を離して遠くしたほうがいい理由も同じです。
さいごに
ミスしたくてミスしてるわけじゃないのに、周りからとやかく言われると腹が立ったり萎縮したりしますよね。
信頼できる人のアドバイスなら素直に聞くべきですが、自分の感覚のみを頼りに生半可な知識を押しつけてくる人は無視したほうが賢明かもしれません。
かくいう私も他人に偉そうに指導できる立場にないので、こういう考え方もあるよ、程度に聞いておいてもらえるといいと思います。
周りの声に圧されて伸び伸びプレーできない人や、コンパクトに手首を使って返せばボールは安定すると思い込んでいる人には、少し参考にしてもらいたいかなー。